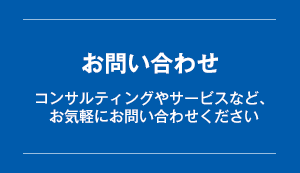皆さんの会社でも、たまにハラスメント事案が起こるかもしれませんね。
そんな時、相談者、行為者、第三者と、色々な人から聞き取りを行うと思います。
私は仕事柄、聞き取り代行を依頼されることも少なくありません。
特に、行為者が役職の高い方だった場合が(これが結構多いのです)
人事の方も、ヒアリングしにくいし・・・というのもあるのでしょう。
また、最近では「相談受付担当者向け研修」というのもオーダーが増えて、
人事の限られた人だけでなく、労働組合の役員さん、その他
複数の人ができるようになっておこう、という動きもあります。
私も、依頼されれば、相談受付担当者に必要とされるスキルや
ヒアリングのコツなど、一生懸命お伝えするんですが、
一度練習したからといって、すぐにできるものでもないし、
こういう事案は、毎週起こるわけではありませんので、
実地訓練の機会もそうそうありません。
ということで、半年に一度くらいは、皆さんで集まって自主練習してくださいね、
などと言って帰ってくるのですが、その後どうだかわからない、というのが実情です。
ハラスメント相談やヒアリングで大切なことは、
聞き取る人と、判定する人は別人(別組織)にする、ということです。
聞き取っている最中に、これはハラスメントか、どうか、を考えながら聴くと
どうしても、そちらに気を取られてしまい、丁寧な傾聴ができません。
また、聞き取る人と判定する人が同一人物だと、公平な判断が難しい場合もあります。
ですから、相談受付は人事部で、判定は〇〇委員会で、という風に
役割を分けるのが良いのです。
聞き取り役は、ヒアリングに特化して、正確にその内容を判定係に伝えます。
一定規模以上の企業では、ほとんど上記のようにしているはずですが、
難しいのが中小企業です。
役割を分けるほどメンバーがいなかったり、なんでも社長が決めないと気が済まなかったり・・・。
であれば、いっそのこと聞き取りは完全に外部に委託するのも一つの選択肢かもしれません。
相談者、行為者、関係者のすべての聞き取りを外部に任せ、詳細で正確な報告書を受け取ります。
それをもとに、社内で判定をする、というのもよいでしょう。
ハラスメントの聞き取りは、割と負担の大きな仕事ですし、それなりのスキルも必要です。
何事もスキルを習ったら、どんどん練習して身に着けるものですが、
こればかりはそうもいきません。
ですから、外注もありかな、と思う今日この頃です。